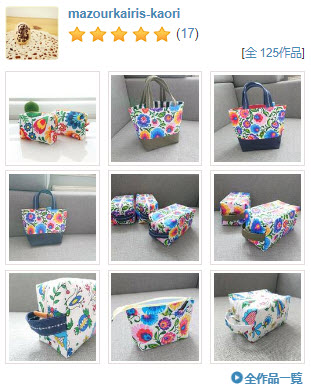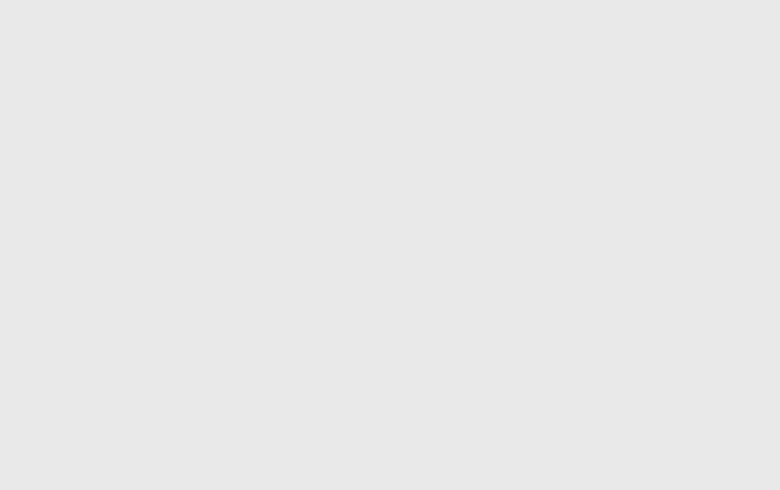10月前半はガイドのご依頼をたくさん頂き、お蔭様でちょっと忙しくしていました。
皆様ショパンコンクールのためにワルシャワへ来た方々。
以前素人目線からのレポートを書きましたが、
皆様からお話を聞いてから読み直したら大変失礼な内容ではないかと思いました。
無知な私ですが、
ショパンについて、ショパンコンクールについて、いろんなお話を聞くと、
皆様の思いが伝わり、一般的なコンサートではないということに違いはないのですが、
ただ専門的な人たちの集まりではなく、
その場は夢を叶えられるすばらしい場だとわかり、
その場に一緒にいられるということは幸せなことだとも思うことができました。
日本中のピアノの先生のつながりや、
応援している家族の方々、生徒の方々、たくさんの人がワルシャワの会場内だけでなく、
インターネット配信を通して世界中から応援している方もいるなど色んな事を知り、
私は日本にいたらきっと関わることはなかったであろう方々から沢山の刺激を受けて
興味がとてもわいてきました。
ご一緒した方の中には5年後のショパンコンクールを目指している方もいらっしゃいました。
私もこれから応援団の一人として、5年後を楽しみにしております!!
さて、今日は3次予選前の中日でお休みだそうです。
明日からいよいよ3次予選。
日々の演奏者の写真はショパン協会の方が毎日facebookに投稿
されていますので、是非ご覧になってみてください^^
★ https://www.facebook.com/instytut.chopina ★
3次予選へ通過した方のリストが出ていました。
Mr Luigi Carroccia (Italy)
Ms Galina Chistiakova (Russia)
Mr Seong-Jin Cho (South Korea)
Mr Chi Ho Han (South Korea)
Mr Aljoša Jurinić (Croatia)
Ms Su Yeon Kim (South Korea)
Ms Dinara Klinton (Ukraine)
Ms Aimi Kobayashi (Japan)
Mr Marek Kozák (Czech Republic)
Mr Łukasz Krupiński (Poland)
Mr Krzysztof Książek (Poland)
Ms Kate Liu (United States)
Mr Eric Lu (United States)
Mr Szymon Nehring (Poland)
Mr Georgijs Osokins (Latvia)
Mr Charles Richard-Hamelin (Canada)
Mr Dmitry Shishkin (Russia)
Mr Alexei Tartakovsky (United States)
Mr Zi Xu (China)
Mr Yike (Tony) Yang (Canada)
19歳の小林愛実さんが3次予選まで残りました!!
最後までやり切って欲しいですね。
国によって、育て方が違うという話も聞きました。
こちらのほうでは「あなたは才能ないからやめなさい」と早々にきってしまうとか。
しかしその分、才能を見出されたらその子はまさに本物、
というような教育法だそうです。
そんな見出された方々がこうして出てくるのでしょうね。
ポーランド人が意外といますが、
そもそもピアノが家にある人なんてどれくらいいるんだろう?
ショパンがいた時代は、ポーランドは裕福だったと思います。
その後国がなくなり、国が持ち直したとしても、今度は世界大戦があります。
近代史で言えば、ポーランドに来た事がない人の想像通り貧しい国です。
ピアノなんてある家は、よっぽど昔からお金持ちか、
音楽家の家系か、とても恵まれた人です。
そんなに友達が多いわけではありませんが、友達の友達まで見ても、
「ピアノを弾ける人いる?」と聞いて、弾ける人にあたったことがありません。
ただ、家にピアノがある人にはあたったことがありました。
もちろん調律はされていなかったのですが、何か弾いてと言われてエリーゼのためにを弾いたら、
椅子を持ってきて友人夫婦のほかにもお母さん、おばあちゃんもきて、
「もう一回弾いて!」とアンコールをもらったことがあります。
日本ではピアノは女の子の義務的な趣味のようなものですもんね。
そんな話をしたらびっくりされましたよ。^^;
ジェラゾヴァヴォラに行った方なら、ワルシャワがどれだけ異質で都会かというのは
お気付きになられたかと思います。ジェラゾヴァヴォラのあのような雰囲気、あれがポーランドの普通であって、ワルシャワ・クラクフのような大大大都会は異質なのです。
学校でも音楽は、どちらかというと歴史として習うようです。
なので、人物と曲は知っているそうですが、自分が演奏するようなことはあまりないようです。
そういえば、私がいた中学校は秋の学際は合奏祭でした。
多くの学校は合唱祭とあとで知り、びっくりしました。歌なのか!と。
合奏祭だと、もちろん吹奏楽部が多くいると有利なのですが、
中学1年生から和太鼓やティンパニ、サンバホイッスルなど関係者以外はおそらく一生触らないであろう楽器に触れる機会でしたので今思えばいい経験だったと思います。
ポーランド人の主人(同年)はというと、そもそも楽器を全然知りません。
学校ではリコーダーならやった、といっています。鍵盤ハーモニカはやってないようです。
木琴は?鉄琴は?オルガンは?
・・・オルガンは先生がたまに弾けたかな~。
出来る人がいるとしたらバイオリンかな~ギターが一番ポピュラーかな~?
ピアノよりバイオリンか・・・確かに場所は必要ないし、重くもないし、どこでも出来るし、
ヨーロッパならではなのかもしれませんね。
学校によっても全然違うそうですが、ポーランドの教育が気になってきます。
音楽はやっぱりお金がかかりますよね、その点できっと今の子供たちは
1日学校見学してみたいです。
話がそれてしまいましたが、
今年の優勝者が決まるまで目が離せませんね!
そして今から5年後のショパンコンクールも楽しみです!!
余談ですが、風邪を引いてしまい帰ってきてから寝込んでいました。
皆様にいただいた簡単におかずが作れるものやポカリ、経口補水液の素、マスクなどなどのおかげで助かっております。
37度程度の熱が続いているのが不思議なのですが、ちょうどガイドもないので家で休もうと思います。
ショパンめぐり日記や、クラクフ同行日記を書きにまたすぐ戻ってきます!